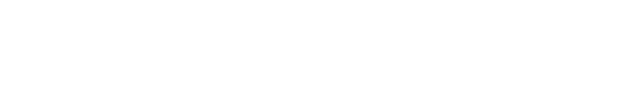3人の師匠に育てられて今がある
いつも当クリニックのHPを閲覧いただきありがとうございます。
先日、スーパーで買い物をしていて たまたま他病院の形成外科の先生に会い、このブログを結構見ているとのことで、多少医療関係者向けにも書かせていただきたいと思います。
大学4年生の時に講義で感銘を受け、形成外科医を目指していました。だから自分も大学で講義をお願いされたときはそういう医学生が一人でも現れてほしいとの思いで8年ほど担当させていただきました。
当時は県内に形成外科医を育てるシステムが無かったこと、最新の形成外科技術を身に着けようと、大学卒業後は東京の大学病院の医局に入局・就職しました。
これまで沖縄のぬるま湯環境で育ってきた自分にとって、いろいろ衝撃的でした。医局員は皆、論文片手に勉強しながら仕事してました。全く帰らず泊まりで論文を書いたり研究している先輩も一人や二人ではありませんでした。(いまや彼ら先輩・同僚のほとんどが大学病院の教授・准教授になっています。)
当時の病院には毎日のように全身熱傷患者や、手指の切断に対する再接合術の緊急手術患者が運ばれてきていました。
新しい環境で心を許せる友人もおらず、衝撃的過ぎてホームシックになり、一度沖縄に帰ったほどです。3日ほどで戻りましたが、、、
同期は12人が入局を希望し試験、面接を受け、6人が合格し入局を許されました。その結果5人が実際に同期として入局しました。(今ではシステムが変わり、大学病院の医局に入局する医師は確実に減っているので、大学病院にとってそのようなぜいたくな選べる環境は今では考えられない状況です。)
その後1人減り、2人減り、、、となって自分も今は沖縄に戻り大学を離れたということになりますので同期で大学病院に残って頑張っているのは現在准教授であるH先生だけです。同期がもう教授に手の届くところにいて頼もしい限りです。
あとで聞いたのですが、決して良い印象ではなかった田舎者である自分という人間が、なんのツテもなく東京女子医大への入局が許されたのは、当時の医局長である日本大学名誉教授の仲沢先生が、自分の足元をみて、きれいな靴を履いていたから、、、、とのことでした。面接態度が合格であったということでしょうか。これが最初の師匠との出会いです。
1年間死に物狂いで勉強しました。できるだけ当直し大学に寝泊まりして医局に1970年代の形成外科開設から保管されている過去の先輩方の手術記録や医学論文を読み漁ったり、夜中は顕微鏡手術の練習として、最初は直径2mmほどのシリコンチューブの吻合から始まり、やがて許可されラットの血管吻合を行ってマイクロサージャリーの修練を積んだり、救急外来で積極的に皮膚縫合を行ったりして技術を磨いていきました。
2年目には、入局を許していただいた当時医局長の仲沢先生が部長をされていた鹿児島市立病院に追いかけるように異動となりました。そこでは一般外科研修もしながら、形成外科医としての基礎的な手術をたくさん執刀させていただきました。周りの先輩ドクターたちが執刀しようとしても仲沢先生が、「これは東盛に執刀させなさい」とツルの一声で一番下っ端の私に執刀権を譲っていただき必死に勉強しながら執刀したものです。おかげで当時の同期とは比べ物にならないくらいの経験がつめたと思います。しかしながら、仲沢先生は、特に手術室や患者を診察しながら教科書や論文を開くことは固く禁じていました。執刀前にすべて頭に入れてのぞみなさいということです。先輩先生が参考書片手に手術をしていてきつく怒られていました。まあ患者さんもそういうの見ると良く思わないですよね。
夜も当時鹿児島最大の繁華街である天文館の居酒屋で説教交じりの指導が続き、物事の考え方の基礎を学びました。さらに仲沢先生が東京都立川市の災害医療センターに異動となり、それを追いかけるようにして(呼んでいただいたのでしょうか)自分も異動を命じられました。
災害医療センターは多摩地区でナンバーワンの救急車の受け入れ数(年間約10,000件)を誇っており、外傷外科の宝庫でした。救急車が5台くらいならんでいるのはざらでした。救急センターは救急医療で有名な日本医大からの派遣医でみな目がギラギラしてました。テレビに出るような先生も何人かいました。その中で鹿児島での経験にも増してたくさん手術を執刀させていただきました。医局のデスクで隣にいらした脳外科のY先生はドイツ留学を目指し猛勉強しながら夜は脳出血などの緊急手術対応しており、圧倒されました。よく救急整形外科の先生と開放骨折に対する手術のコラボレーションしていたことを思い出します。当時は珍しい自動心臓マッサージ機器もこの時初めて見ました。
重症熱傷はよく経験しましたが、救急の先生方も熱傷を専門としている先生がいらっしゃったので、「バチバチ」にやりあってました。ただ、女子医大の形成外科の初代教授であられる故 平山先生、2代目野崎先生、そして当時部長の仲沢先生が日本熱傷学会では重鎮でありましたので、形成外科が強い勢力を誇っていました。
ある日、仲沢先生執刀の手術の助手に入ることになり、「どんなすごい手術になるのか勉強させていただこう」という気持ちで手術に入りました。足のゆびが6本ある症例の手術でした。最初に開口一番仲沢先生より「さあ、どんな手術をする。デザインしてみなさい。」と言われ、執刀の心構えが全くできてなかった自分は頭が真っ白になり、何もできませんでした。次に「手術室から出ていきなさい。そしてこの手術の勉強をしてわかったら戻ってきなさい。」と言われ、すぐに自分のデスクに戻って勉強し、手術室に戻ると仲沢先生は無視して手術を開始していました。後ろで立ちすくんでいた自分がいました。雰囲気の険悪さを見かねた看護師が「東盛先生戻りましたよ。」と仲沢先生に告げると、先生は「出て行って他の先生と代わって外来の手伝いしながら反省してきなさい。」と言われ手術に参加することはできませんでした。
非常階段で悔し泣きしました。「たとえ第2,第3助手でも執刀医が倒れたら手術をしなくてはならない。その心構えは常に持っていつでも執刀できる勉強をして準備しておきなさい。」という見せしめをすることでの(厳しい?)指導でした。
それからはいつ任されてもいい様に予習は欠しませんでした。外科医としては当たり前の態度だと思いますが、こんな指導をしてくれる先生は今はいないでしょう。下手すると無勉強で(なんか与えて・教えて)くれくれ若手医師にパワハラ扱いされるかもしれません。しかし自分には今でも忘れることができない、成長するための貴重な経験でした。
学会発表も一から手ほどきを受け、日本形成外科学会や熱傷学会、マイクロサージャリー学会を中心に発表させていただきました。そこでは座長の大御所の先生にもきつい指導を受けながら成長している自分も感じましたし悔しい思いもしました。英会話もままならない自分に海外での英語での発表もいくつか課されました。海外のドクターからの質問はその英語のスピードに理解できず完敗でしたがとても貴重な経験でした。
ドクター5年目で再び大学に戻りました。そこでは3代目の櫻井教授体制で、また別の厳しさがありました。誰よりも率先して患者のことを把握し、常に最新の術式をブラッシュアップする心構えで臨床家としてとてもお手本になる教授でした。「その患者はどこに住んでいて、仕事は何をしている?」が口癖の先生でした。それは手術に際して術式の選択、どこまでの手術を望むか、また術後通院のことなどで把握しておくことはとても大事なことです。それを知ったうえではじめて患者個々に合わせた対応ができます。今のクリニックにも生きています。ありがたいことに、離島や北部からも患者さんが来てくれていますので、それに合わせた診療が必要になります。これが第2の師匠との出会いです。ある程度デキル気になっていた自分はそこでまた奈落の底に落とされました。医師として、臨床家としての心構えがなってないと常にお叱りを受けながら育ちました。学会発表も妥協を許さぬ姿勢で、学会発表前日まで櫻井先生の宿泊先に呼ばれて修正、指導を受け、ぎりぎりまで発表をより良くしようとする姿勢はすごかったです。いかに大変であったかは推測できるでしょうか。学会って、、、遠方に行って、ある意味、ご当地ならではの食事や観光も兼ねたい、、、、という気持ちがありましたが、観光気分は吹っ飛びました。
いつも難しい再建手術ばかり執刀する先生であったためその助手も体力勝負です。朝から執刀開始し、夜中の0時を超えることもしばしばでした。そこから一緒に反省会と称して朝方まであいている四谷の羅生門という焼肉屋さんで手術の話をしながら明日への力を蓄えてました。それはそれで体力的にきつかったです。最も長かった手術は、朝から始まり、次の日の9時の外来直前まででした(というか、9時を少し過ぎてました)。教授は終わった後、手術室の更衣室に置いてあるベンチで10分ほど横になって、そこから着替えて外来に向かいました。
自分はその時はまた朝から別の手術の助手でした。今の若い先生には信じられないかもしれませんし問題かもしれませんが、それはそれで貴重な経験で医師としての成長を感じることができた時間でもありました。
また、詳細は割愛しますが、私が巻き込まれた困難なケースでも、周りの同僚や先輩たちが一歩引いているなか、櫻井教授だけが親身になって一緒に対応してくれて、とても心強かったです。自分の後輩が同じような困難に立ち向かった時に経験者としてサポートできる、そういう先輩になりたいと思いました。
そして、私が2年後に沖縄に戻ると決まり、それまでの間、野崎名誉教授の大学病院として最後の勤務である外来の助手を2年間務めたことが一つの大きな経験となりました。先のお二人の先生の師匠ですから、年功序列的に順序は違いますが第3の師匠です。野崎先生は教授時代には、私の様な若い先生がしくじっても決して叱咤せず、その指導医に矛先が向いておりましたので、孫の様な扱いを受け、それまで密にかかわることはありませんでした。だから順序が違っています。野崎名誉教授は日本形成外科学会の重鎮で、若い先生は知らないかもしれませんが、学会の礎を作った先生のおひとりです。今では20年目を迎えようとしている「日本創傷外科学会」を立ち上げた方です。そして、人生経験が豊富です。面と向かって話をすると、全てを見透かされたような気持になり、一ミリでも自分にやましいことがあるとその目を直視できません。
先生の外来では、長年診てきた患者さんの経過観察と、社会的に著名な患者さんの手術対応が主でした。野崎先生は、教授職を降りてからは名誉教授として普段は学会関係やほかの施設で仕事され、大学病院では週に1回外来と手術執刀され、いまだ多忙な方であったため、円滑に診療ができるよう、外来の助手として手術症例のプレゼンテーションを事前に資料を作成しメールしたり、手術助手をすべて行っていました。また、先生の外来で補助として後ろから見ていて、患者さんへの一言一言は重く心につきささり、不安が一気に解消され、涙をぬぐう患者さんを多く見てきました。なんという外来だ!!と感銘を受けました。
某大手の美容クリニックで顔にレーザー治療を受けて深いやけどのキズアトをおってしまった20歳代前半の女性が泣いて野崎名誉教授の外来を受診されましたが、野崎先生の言葉を聞いて笑って帰りました。驚愕です。
野崎先生には、私が若いころから、「お前は沖縄の王子になるんだ。」と、琉球大学の教授になることを期待されておりましたが、もともと入局時から将来は沖縄で地元に貢献する臨床医になりたいと大学に伝えておりましたので初志貫徹することにしました。
教授になると学会参加が必須であり、診療に割く時間は半分以下となり、家族もないがしろにせざるを得ない場面も多く出てきてしまうことを師匠たちから学ばせていただきましたので、どうしても医師になるときから地域貢献として臨床医になる夢を捨てきれずそれだけは我を通してしまい申し訳ない気持ちです。そのために早くから海外留学のお誘いとして肩を叩かれたりしましたが断ってしまいました。
この経験が今に少なからず生きていると思っています。
沖縄に戻る時には快く送り出していただきました。症例の治療に困ったら執刀に行くからいつでも呼んでと野崎先生に言われて送り出していただきました。
実際に、全く呼ばないのは失礼かな、、、、と思い、帰沖3年後に連絡してみると「私がやることはないよ。トンさん(私の野崎先生からだけのあだ名)は何でもできるから頑張れ!」と言われた言葉で、大学病院からのある意味卒業になったのかなと思いました。のちに「トンさん」というあだ名はいまの大学病院の同門会長の東山先生のあだ名であったことが分かりました。
今でも入局した医局に間違いはなかったと思っています。大学病院離れが進んでいる今の若い先生にはぜひ一度は所属してもらいたいと思います。しかし、そこで自分のやりたいことを見つけられれば、それを得意としている他施設(場合によっては海外)で直接見て、学んでくるのが最も近道だと思います。どこの施設も快く引き受けてくれると思います。
とくに海外留学を目指していれば、大学の教授は学会を通じて海外の先生とも知り合いが多いので最も近道だと思います。
ブログは毎月1日と15日に発信してまいります。