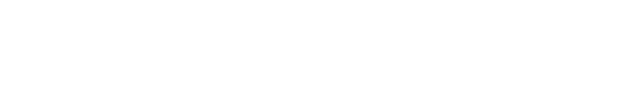下肢静脈瘤
下肢静脈瘤とは!?
沖縄県内では、どこで診てもらったらよいかわからないというお声をよく聞きます。現状、当科ですべての治療が行えるわけではありませんが、ほとんどの例で治療可能ですので、お気軽にご予約の上相談にお越しください。
時々メディアでも取り上げられており、ご存じの方も多いと思いますが、脚の静脈がぼこぼことこぶのようになったり、くもの巣や網目状に血管が浮き上がって見える状態です。これは、見た目の問題もありますが、そうなる主な原因として、大伏在静脈や小伏在静脈など皮膚から浅いところにあるいわゆる表在静脈が正常に機能しなくなり、酸素を消費した静脈血を肺に戻せず逆流して脚にたまっている(うっ滞)している状態で、静脈が血液で満たされてぱんぱんにはれ上がっている状態です。そして、その逆流した静脈の枝となる静脈が、さらに皮膚から浅いところにあるので浮き出たりくもの巣状に見えたりすることになります。もともと原因となる逆流の強いこれら表在静脈を治療しない限り、表面に見えているぼこぼこ血管の治療を行っても再発したり、新たに病変が出てきたりしますのそ、表在静脈の治療が先決です。
また、ふくらはぎの筋肉は、体でいう心臓の役割を担っており、歩くことによるポンプ作用で静脈を圧迫し肺へと静脈血を押し上げています。したがって活動している日中にはポンプ作用で静脈の流れが保てるので、症状があまり出ないことが多いです。しかし、静脈に存在している逆流しないための「弁」が存在していますが、それが立ち仕事や趣味などで脚に長期間負担がかかる生活を続けると機能しなくなり、逆流するようになります。その状態が続くと、酸素のない、栄養のない静脈血がたまっているわけで、様々な症状が出てきます。特に夜間に症状が出やすくなります。
こむら返り
ふくらはぎの筋肉がつります。日中は活動することによる筋ポンプ作用で症状があまり出ず、静脈血のうっ滞により主に寝ているときにおこります。
むくみ
静脈のながれがわるいことで脚全体の血流がとどこおり、むくみが出てきます。スネを指で押すと皮膚がしばらく陥没したままになることで診断されます。
※むくみの原因はほかにもリンパ浮腫、心不全、腎不全、低栄養などいくつかあります。
皮膚症状
皮膚のかゆみがでてきたり、脚の内側が黒ずんできたりしてきます。進行すると脚全体にシミが広がったり、ぶつけたりしていないのに脚の内側にキズができてきたりします。
炎症症状
酸素のない静脈血流で満たされた脚は、皮膚に十分な酸素が行き届いていない状態なので、感染に対する抵抗性も悪化します。皮膚には常在菌が存在しているため、免疫や抵抗力が落ちると皮膚の感染(蜂窩織炎)をきたしやすくなります。
血栓症状
静脈の流れが悪くなると血が固まりやすくなり血栓ができやすくなります。それでみられる症状は局所の痛みと赤み、腫れです。さらに血栓が肺に流れてしまうとエコノミークラス症候群に代表される肺塞栓症という病気になります。そうなると息苦しくなり血栓を溶かしたり、取り除く治療が必要になることがあります。
下肢静脈瘤は、基本的には自然に良くなることはありません。徐々に悪化することがほとんどです。
40歳以上の約10人に1人、妊娠・出産の半数におこるとされており、重症化するとたいへんですし、軽症の状態でも見た目の問題があり、治療の必要性が認識されてきています。
治療
弾性ストッキングや弾性包帯などによる圧迫治療
圧迫することで表在静脈の静脈血が深部静脈に誘導され、脚全体の静脈の流れをよくする治療です。直後から改善が自覚されます。しかし、日中はずっと着用することが勧められますので、沖縄の暑い環境ではとてもツライのが現状です。また、包帯などは永年使用できるものではないので買い替えもコスト的に馬鹿にはなりません。
・弾性包帯1巻約500 円、らばらば(弱圧ストッキング)1足約2,600円(サイズにより若干変わります)
・アルケア弾性ストッキング1対約 4,000 円
・シグバリス(上質の弾性ストッキング) 1足約5,000-15,000円(種類で異なります)
手術
①日帰り手術:血管内塞栓療法
いわゆる「グルー治療」と呼ばれているものです。日本では現在はVenaseal®という機器のみが2019年12月から保険適応であり、当クリニックでもこれを用いて行います。本治療は
● (レーザー治療で起こりうる)熱による静脈周囲(筋膜や皮膚、神経など)の損傷がない!
● TLA麻酔(血管周囲に局所麻酔を行う麻酔方法。レーザー治療では周囲組織の炎症を防ぐためにも必須。)が不要!
● ほかの治療では必須の術後の包帯やストッキングによる圧迫が不要!
という大きな利点がありつつ、欧米での治療成績では、術後5年の成績(再発率が数%)がレーザー治療に引けを取らないことが報告されており、海外に始まり、現在日本でも急速に広まりつつある治療です。
適応
・大伏在静脈と小伏在静脈
※日帰り手術であり、保険適応の観点から、左と右、大伏在静脈と小伏在静脈はそれぞれ1回の手術で1カ所づつ行っております。
・エコー検査で太い静脈(直径18mm以上;めったにありません!):現状はハートライフ病院へ紹介させていただき院長が執刀します。
慎重適応
・下肢に蜂窩織炎や感染などが存在する場合
・現在落ち着いていない膠原病やアレルギー疾患がある場合
・シックハウス症候群の既往がある場合
・まつげエクステンションや人工爪などの施術者(接着剤との兼ね合いです)
・深部静脈血栓症の既往を持つ場合
・19歳以下
適応外
・接着剤(シアノアクリレート系)アレルギー
・前伏在静脈・穿通枝静脈・伏在静脈の筋膜よりも表在にある静脈(海外で有効例の報告はありますが国内では安全性が確立されておりません)
・血栓症になりやすい疾患を有する場合(抗リン脂質抗体症候群など)
・多発・再発性表在静脈血栓症(単発であれば落ち着いたら治療を行うことは可能です。)
治療の流れ 通常治療は約30分、来院から帰宅まで約1時間
・当日は朝食はごく軽めに(静脈麻酔の場合には朝は禁食、水分のみ)
・来院、着替え、手術室で横になって院長がマーキングし消毒
・カテーテルを刺す部位に局所麻酔の注射
・治療(痛みは通常ありませんので何かあれば声かけしてください)
・治療終了し刺入部には圧迫ガーゼ
・着替えて歩いて帰宅。鎮痛剤は希望あれば処方します。軟膏などは通常不要です。
・当日夕方からシャワーは圧迫部を保護すればOKです。翌日から圧迫を解除し、特に制限はありません。飲酒や入浴、サウナなど温まることも翌日からOKです。
・1週間後に術後最初の診察にお越しください。※何かあれば早めに受診をお願い致します。
②血管内焼灼術(レーザーや高周波による治療)
いわゆる「レーザー治療」と呼ばれているものです。主に熱源として、レーザーと高周波による機器の2種類が日本で行われていますが当院では、高周波による血管の焼灼を行うClosureFastカテーテル®を用いた施術を行っております。
本機器は、5年で92%の閉塞率を持つ高い治癒率を誇る機器で世界で使用されています。
血管内塞栓術で対応できないような比較的太い静脈が適応になります。
院長も血管内焼灼術の指導医として1000例以上の多くの手術を行ってきました。
局所麻酔を行い、針を刺し、カテーテルを挿入しますので、キズは2mm 程度で、メスを一切使用しません。ハイリスク例(高度の静脈の蛇行、高度肥満、血栓の既往がある、高齢者、入院希望など)の患者さんは連携しているハートライフ病院で入院手術を行うようにしております。(執刀は院長です)
高周波により静脈の中から血管を焼灼してつぶします。
そしてぼこぼこした血管は元には戻らないので、極小切開(1-2mm)で取り出します。(日帰り手術の場合はリスクを避け、別日に行います。)
治療前
高周波+小切開瘤切除後
一切皮膚縫合もありません。
術後は麻酔が切れたら歩くことができます。日帰り手術の場合には終了後すぐに帰宅できます。
メリット
・傷が小さく縫合不要
・術後の紫斑(内出血)が少ない
・麻酔が切れればすぐに歩行可能
デメリット
・ひざ下の大伏在静脈は神経と並んで走っているのでレーザー治療ができない。(大伏在静脈は太もも部分のみ焼灼することで効果は十分にあります)
・しばらく圧迫(包帯やストッキングなど)が必要(約1カ月を推奨します)。
・皮膚のやけどのリスクがわずかにある。
・血管が蛇行している場合、直径20mm以上の太い場合には適応外。(めったにありません)
手術の実際 手術は約40分です。
御着替え
↓
手術室へ 手術台に横になります
↓
エコーを見ながら院長が治療する予定の血管をマーキング
↓
カテーテルを入れる予定のところに局所麻酔
↓
カテーテル挿入(少し痛みを伴うことがあります)
↓
血管周囲に生食麻酔(tumescent麻酔)
↓
焼灼
↓
カテーテル抜去し、差したところを圧迫固定
↓
包帯圧迫し歩いて帰宅
※ 通常術後1週間で初回来院いただきエコーで治療経過を確認します。術後2回目は1カ月後に来院いただきエコーで最終チェックし問題なければいったん通院終了です。
③伏在静脈抜去切除術 いわゆる「ストリッピング手術」
院長が医師になる前から行われている治療です。逆流している静脈を抜去してしまう方法です。当初よりもだいぶキズは小さくなりました。
現在ではだいぶ少なくなりましたが、①②の治療が難しい場合には今でも行うことが年に1-2回あります。
適応
・①血管内塞栓療法や②血管内焼灼術が難しい例:血管茎が20mm以上や蛇行している伏在静脈など
・①②の治療による再発例(状況により判断します)
適応外
・深部静脈血栓症の既往
・出血素因
メリット
・確実な治療:血管を抜去してしまうので再発はありません。
※表在静脈は数種類あるので、他の静脈が逆流し症状が再燃することはあります。
・直径20mm以上の太い静脈でも治療が可能です。
・下肢にキズがあっても可能です。(炎症がある場合は慎重に判断します。)
・術後圧迫(包帯やストッキング)がしばらく必要です。
デメリット
・縫合がある。(通常大伏在静脈であれば鼠径部は2-3cm、ひざは1cm程度です。皮下のみ縫合しますので抜糸はありません。)
・基本的には連携しているハートライフ病院で入院手術です。
・ひざ下の大伏在静脈は神経とならんで走っているので抜去しません。
・血液をサラサラにする薬を飲んでいる場合には術前に点滴で調整が必要のため入院が長くなります。
※ 高位結紮術(逆流して右いる静脈を糸で縛るだけ)は高率に再発するため行っておりません。いまでも昔他の病院でそのような治療を行われ、再発し治療を行っているケースは多くみられます。
ページ監修医師
東盛貴光 院長 |
|
【経歴】 2000年 東京女子医大病院 形成外科入局 2001年 鹿児島市立病院 一般外科・小児外科研修 2011年 琉球大学病院 整形外科 手外科 2012年 東京女子医大病院 形成外科(手外科・熱傷センター責任者) 2014年 かりゆし会ハートライフ病院 形成外科 部長 2022年 貴クリニック 開設 院長就任 |
|
【主な資格】 日本形成外科学会 指導医・専門医 日本レーザー医学会 指導医・専門医 日本熱傷学会 専門医 日本創傷外科学会 専門医 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術 指導医・専門医 |